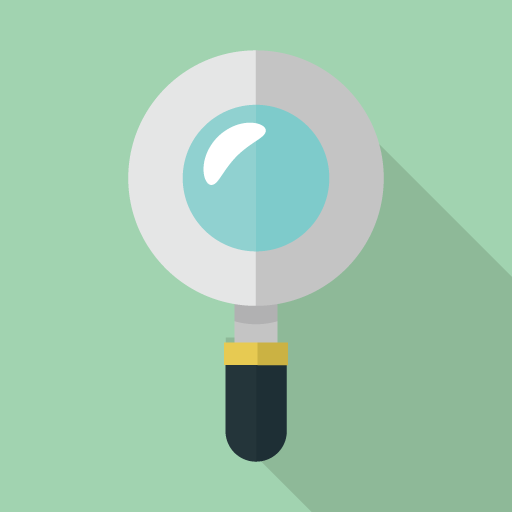歴史的に見れば、宗教は貧困や差別などの社会矛盾が蔓延しているときに拡大してきた。イスラム教やキリスト教、仏教の世界三大宗教ですら例外ではない。宗教は差別や格差などが社会に蔓延しているときに勢力を伸ばしてきたのである。
三大宗教について
イスラム教
イスラム教はアラビア半島の南東部にあるメッカの商人ムハンマドが起こした宗教であり、当時その一帯はインド洋交易の中継地点として大いに栄えていた。莫大な富が都市に流れる一方で、貧富の差が拡大し、貧困が蔓延していた。そうした中で、平等な社会の理想を謳ったムハンマドが貧困層を中心に支持を拡大していった。この宗教の特徴は、稼ぐことを奨励した点にある。だから商人などに受け入れられ、一方で「喜捨」という貧困層への寄付行為も奨励していたので、貧困層にも受け入れられたのである。
キリスト教
キリスト教は、選民思想を持つユダヤ教に対して人々の平等を謳った。神の前での人々の平等という考えは、身分差別や貧困に苦しむ人々にとっての生活の支えとなり、世界中に拡大していった。
仏教
仏教は、人間の価値は生まれや身分ではなく自らの行いによって決まるという主張を持つ。当時のインドでは、バラモン教に基づいた身分制度が厳格に敷かれ、その下で「不可触民」と呼ばれる階層の人々は厳しい差別を受けていた。そうした身分差別に苦しむ人々は人間の平等を説く仏教を受け入れていった。仏教徒はいったんインド国内では消滅するが、やがて20世紀になるとアンベードカルという不可触民出身の人物が、ヒンドゥー教の身分差別に抗議する意味で、多くの不可触民と共に仏教に改宗した。
宗教の機能
このように、宗教は社会矛盾に苦しむ人々を救済し、平等な社会を目指す思想として広まった。その際、宗教は人々の心の拠り所となって彼らを支えた。つまり、宗教とは苦しい現実を生きる上で、「自分が救われる」という希望を人々に抱かせるものである。だからこそ、現実の社会矛盾に苦しむ人々に宗教は受け容れられたのである。その点において、宗教は社会矛盾を是正する調整機能を果たしていたといえる。
しかし、近代以降は世俗化が進行し、現代では社会における宗教の影響力はますます弱まってきている。そして世俗化と共に発達していったのが資本主義である。資本主義の黎明期における格差の拡大はすさまじく、当時の労働者は一日の食事すら満足に取れない者もいた。人々が安価な労働力として酷使され、十分な賃金が払われず、社会的な格差が拡大する中で、そうした社会矛盾を調整するものとして格差を是正し平等な社会の実現を謳ったのは、社会主義思想であった。すなわち、資本主義のもたらす格差を是正し、人々の平等を実現しようという考えである。
社会主義:現代における新たな宗教か
翻って、格差と貧困の問題に悩まされている昨今、世俗化が進み、宗教が非科学的なものと退けられている中で、社会主義がにわかに注目を浴びていることは興味深い。欧州で「社会民主主義」が第三の道として注目を浴び、貧困対策としての社会福祉政策の拡充を求める声は、資本主義的というよりも社会主義的である。超格差社会といわれている現在のアメリカでも社会主義が拡大しつつある。
社会主義は、産業革命がヨーロッパで進展していく中で誕生したが、社会全体が向上している間は顧みられることがなかった。しかし、貧困に苦しみ、社会に不満を持つ人々が増えてきた昨今、彼らにとって社会主義は大いに魅力的な思想なのだろう。宗教は社会矛盾が蔓延しているときに拡大する。ここに宗教と社会主義の共通性が見られるのである。そうした視点から見れば、社会主義も宗教の1つといえるのではないだろうか。